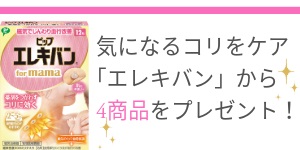祇園祭礼図
元は巻物の信長の遺品。文化活動の交流がもたらした貴重な資料。

粉引茶碗 銘「雪の曙」
石水博物館「伊勢商人川喜田家の茶道具名品」

川喜田半泥子 千歳山窯 昭和10年代 高さ10.0センチ、口径14.3センチ、高台径5.1センチ 石水博物館蔵
柔らかな白色と、焼成中の窯変(ようへん)がもたらした淡い桃色。「雪の曙(あけぼの)」の銘の通り、積もった雪の上に朝の光がさしこむ情景が浮かぶ。
作者は、伊勢の豪商・川喜田家16代当主の川喜田半泥子(はんでいし)(1878~1963)。財界で活躍する一方、陶芸をはじめ書画や俳句など多彩な趣味を持ち、「東の魯山人、西の半泥子」と称された。
茶碗(ちゃわん)の下部にのぞく鉄色の素地は、半泥子の指の跡。釉薬(ゆうやく)をかける際についた指跡がくっきりと残り、新雪についた足跡を思わせる。口縁部はあえて整えずギザギザのまま。「豪快さと繊細さをあわせ持つ、半泥子流茶碗の代表作」と学芸課長の龍泉寺由佳さんはみる。
指跡もいとわず手がけた茶陶の銘はほぼ全て自身で付けた。型破りとされるが、「財界人のサロンでもあった茶道に精通しながら、制作は『素人だから』と芯を通していた」と龍泉寺さんは説明する。
(記事・画像の無断転載・複製を禁じます。すべての情報は掲載時点のものです。ご利用の際は改めてご確認ください)
美博ノートの新着記事
-
-
竹一重切花入 銘「音曲(おんぎょく)」 秀吉の小田原攻めに同行した利休作。華麗なる来歴。
-
鰊鉢 ニシンの山椒漬けの保存用に。会津の「用の美」を体現した一品。
-
抱瓶 三日月形の携帯できる酒器。沖縄の風土で練られた手仕事の美。