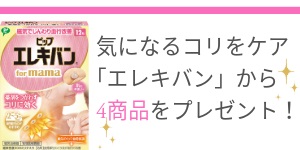石巻市博物館
宿した記憶 どう伝えるか

2011年3月11日、当館の前身・石巻文化センターは津波で床上3.3メートルまで浸水する被害に見舞われました。泥や瓦礫が収蔵庫へ流れ込み、多くの美術作品や史料が被災しました。
収蔵品を救出した活動が「文化財レスキュー」です。全国の大学や博物館、美術館の協力のもと、収蔵品やその破片を捜し出し、洗浄します。その後、修復して安定的に保存できる状態になって当館に戻された文化財は、美術作品だけで246件にのぼりました。
舟越桂(1951~2024)の彫刻「ラムセスにまつわる記憶」は、その1点です。クスノキを使った半身像に彩色し、大理石の目をはめ込んだ作品ですが、表面と胴体内部に近くの製紙工場から流れてきたパルプがからみついて倒れていました。
宮城県美術館に運んで汚れを落とし、東北芸術工科大学で応急処置を施した後、東北歴史博物館で燻蒸しました。大理石の瞳が投げかける眼差しや、薄く彩色された肌の色など、かつての静謐な佇まいがよみがえりました。
震災を通してこの作品に接するとき、タイトルの持つ意味が変わって見えてきます。あの日の「記憶」を宿したことが、この作品が背負った歴史であり、物語なのだと考えています。
石巻出身の彫刻家・高橋英吉(1911~42)の木彫「少女と牛」も被災した作品の一つです。牛の背に乗る少女の左足先が欠損しました。英吉は太平洋戦争で31歳の若さで亡くなりましたが、各地に残された英吉の作品が市に寄贈されたことをきっかけに文化センターが設立された経緯もあり、重要な作家として展示室を設けています。
ほかにも被災の痕跡をとどめる作品は少なくありません。被災の歴史を伝える資料として展示するか、修復して本来の姿に戻すか、関係者には迷いやためらいもあります。被災した作品をどう後世に伝えていくか、模索が始まったところです。
(聞き手・三品智子)
《石巻市博物館》 宮城県石巻市開成1の8(☎0225・98・4831)。[前]9時~[後]5時(入館は30分前まで)。原則[月]([祝]の場合は翌日)、年末年始休み。常設展示室は300円。「ラムセスにまつわる記憶」は所蔵資料展(4月5日~5月11日)で展示予定。

学芸員 小野雄希さん おの・ゆうき 福島県出身。2023年から現職。企画展「移動美術館 佐藤忠良展」などを担当。石巻のおすすめスポットは金華山。 |
私のイチオシコレクションの新着記事
-
台東区立一葉記念館 枠外までぎっしりと。肉筆が伝える吉原周辺の子どもたちの心模様。
-
京都国立博物館 中国・唐と日本の技術を掛け合わせた陶器「三彩蔵骨器」。世界に日本美術を体系的にアピールするため、「彫刻」として紹介された「埴輪(はにわ)」。世界との交流の中でどのようにはぐくまれてきたのでしょうか?
-
昭和のくらし博物館 今年は「昭和100年」ですが、昭和のくらし博物館は、1951(昭和26)年に建った住宅です。私たち小泉家の住まいで、往時の家財道具ごと保存しています。主に昭和30年代から40年代半ばのくらしを感じられるようにしています。この時代は、日本人が最も幸福だったと思います。日本が戦争をしない国になり、戦後の混乱期から何とか立ち直り、明るい未来が見えてきた時代でした。
-
国立国際美術館 既製品の中にある織物の歴史や先人の営みを参照し、吟味し、手を加えることで、誰も見たことのないような作品が生まれています。
新着コラム
-
グッとグルメ 羽田美智子さん 吉祥寺MATSUHIRO 吉祥弁当 私が主演する舞台のときに差し入れたら、グルメな先輩たちが「みっちゃん、今日のお弁当、最高!」なんて口々に言ってくださったんです。私の勝負弁当の一つなんです。
-
グッとグルメ 横尾初喜さん
レストラン蜂の家 ビーフシチューとハンバーグ煮込み 映画監督の横尾初喜さん。出身地である長崎県佐世保市のお店で食べる「ビーフシチューとハンバーグ煮込み」が撮影の支えだそうです。 -
-