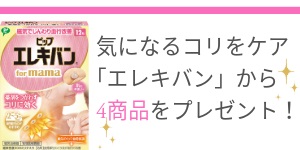宮川香山眞葛ミュージアム

陶芸家の初代宮川香山(1842~1916)が横浜に開いた真葛(まくず)窯は、輸出陶磁器を多く産出しました。国内にはほとんど現存しないため、海外から買い集め、常時100点ほどを展示しています。
香山は、フィギュアのような造形と精緻(せいち)な金彩の細工を施す「高浮彫(たかうきぼり)」を生み出しました。1871年に開窯した当初は、高浮彫を多く手がけましたが、81年ごろになると作風が一変します。「磁製緑釉蓮画花瓶(じせいりょくゆうはすがかびん)」は、その一つです。
生命力にあふれ咲き誇る花びらと重そうに首をもたげる茎の様子が対照的で、日本の美意識をほうふつとさせます。描かれた花や茎の形状にあわせ、足元にいくほどなだらかにすぼまる器は、巧みなろくろの技によるものでしょう。
つやのある透明釉(ゆう)に封じ込められた色彩が、幻想的でたおやかな風情を演出しています。「釉下彩(ゆうかさい)」という技法で、顔料で絵付けをした後、透明釉をかけ高温で一気に焼き上げます。一般的に顔料は色ごとに発色温度が異なりますが、香山は試行錯誤を重ね、透明釉と同じ温度で多彩な色が発色する方法を開発しました。
高浮彫は繊細で壊れやすく、制作に時間がかかることが欠点でした。人気の陰りをいち早く察知した香山は、次の売れ筋を中国・清朝の古陶の趣とみて、研究開発に没頭。当時流行のアールヌーボーを採り入れながら、独自の釉下彩を生み出したのです。
高浮彫、釉下彩を究めた香山は、晩年に二つの技法を融合させた「琅かん釉蟹付花瓶(ろうかんゆうかにつきかびん)」を作り上げました。
きゃしゃな足を縁にかけたカニが、今にも器を乗り越えていきそうです。釉下彩で爪や甲羅を染め分け、実物にせまる表現力にほれぼれします。器の内側にかかった釉薬は青みを帯び、たっぷりと水をたたえたような仕上がりに。初代香山の遺作となりました。
1945年の横浜大空襲で3代宮川香山が落命、窯は焼失しました。今では幻のやきものとしてその名を刻んでいます。
(聞き手・鈴木麻純)
《宮川香山 眞葛ミュージアム》 横浜市神奈川区栄町6の1(☎045・534・6853)。土曜、日曜のみ開館、午前10時~午後4時。800円。2点は常設展示。企画展「でかっ、ちっちゃ」を開催中(~12月8日)。

館長・山本博士さん やまもと・ひろし 2009年にミュージアムを開設し、以来館長を務める。本業の製菓業の傍ら、真葛焼の調査、収集、保全を手がけ、横浜市の文化事業にも数多く携わる。 |
私のイチオシコレクションの新着記事
-
台東区立一葉記念館 枠外までぎっしりと。肉筆が伝える吉原周辺の子どもたちの心模様。
-
京都国立博物館 中国・唐と日本の技術を掛け合わせた陶器「三彩蔵骨器」。世界に日本美術を体系的にアピールするため、「彫刻」として紹介された「埴輪(はにわ)」。世界との交流の中でどのようにはぐくまれてきたのでしょうか?
-
昭和のくらし博物館 今年は「昭和100年」ですが、昭和のくらし博物館は、1951(昭和26)年に建った住宅です。私たち小泉家の住まいで、往時の家財道具ごと保存しています。主に昭和30年代から40年代半ばのくらしを感じられるようにしています。この時代は、日本人が最も幸福だったと思います。日本が戦争をしない国になり、戦後の混乱期から何とか立ち直り、明るい未来が見えてきた時代でした。
-
国立国際美術館 既製品の中にある織物の歴史や先人の営みを参照し、吟味し、手を加えることで、誰も見たことのないような作品が生まれています。
新着コラム
-
グッとグルメ 羽田美智子さん 吉祥寺MATSUHIRO 吉祥弁当 私が主演する舞台のときに差し入れたら、グルメな先輩たちが「みっちゃん、今日のお弁当、最高!」なんて口々に言ってくださったんです。私の勝負弁当の一つなんです。
-
グッとグルメ 横尾初喜さん
レストラン蜂の家 ビーフシチューとハンバーグ煮込み 映画監督の横尾初喜さん。出身地である長崎県佐世保市のお店で食べる「ビーフシチューとハンバーグ煮込み」が撮影の支えだそうです。 -
-