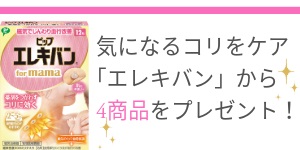遠野市立博物館

来年で生誕150年を迎える、日本民俗学の父・柳田国男。当館は、柳田が著した「遠野物語」の舞台、岩手県遠野市に日本初の民俗専門博物館として1980年に開館しました。
1910年に刊行された遠野物語は、柳田が遠野出身の佐々木喜善という青年から聴いた伝承を記録した説話集。カッパや天狗(てんぐ)、山男などの怪奇譚(たん)が記されますが、実在の村人や場所、特定の年代が登場し、実話として語られているのが大きな特徴です。
遠野を含む東北地方には「オシラサマ」という民間信仰が今に残ります。養蚕や目の神、吉凶を「お知らせ」する神様として家に祭られています。ご神体は桑の木の枝に馬と女性の頭を彫った一対のものが知られますが、男女の顔をした像や、3体以上で1組のものもあり、家によってさまざま。遠野物語には、このオシラサマ信仰の始まりが書かれています。人間の娘と馬が恋仲になるものの、怒った娘の父親が馬を桑の木につるして殺(あや)めてしまう。悲しんだ娘は切られた馬の首に乗って天へ昇ったという話です。写真の「オシラサマ」は、遠野のある家に病人が出た際、イタコの言う通りに川へオシラサマを流したものの、再び病人が出たために作り直した像です。毎年の祭日と呼ばれる日にオセンダクという布が新しく着せられ、顔にはおしろいが塗られました。
遠野物語には山の神も度々登場します。この「山の神像」が納められた厨子(ずし)には「十二月十二日」と記されていますが、この日は山の神の祭日で、入山は禁忌。山の神が木の数を数える日で、木と間違えられた人間は二度と山から下りられないと伝わるためです。今でも遠野の林業関係者はそれを守っているのだそうです。
私も遠野出身ですが、神様など目に見えないものを信じる風習が地域に根付いているのを感じながら育ちました。遠野物語の魅力は、そんな現世と異界の間にいるような不思議な作品世界。ぜひ展示資料から感じ取っていただければと思います。
(聞き手・中村さやか)
《遠野市立博物館》 岩手県遠野市東舘町3の9(☎0198・62・2340)。午前9時~午後5時(入館は30分前まで)。310円。原則月曜と月末日、年末年始休み(4月は無休、5~10月は月末日のみ休み)、その他定期休館日あり。

主査兼学芸員 浅沼聡美さん あさぬま・さとみ 岩手県遠野市出身。専門は民俗学。遠野の旧家などを訪れ、現地調査、民俗資料の保存活動を行う。 |
私のイチオシコレクションの新着記事
-
台東区立一葉記念館 枠外までぎっしりと。肉筆が伝える吉原周辺の子どもたちの心模様。
-
京都国立博物館 中国・唐と日本の技術を掛け合わせた陶器「三彩蔵骨器」。世界に日本美術を体系的にアピールするため、「彫刻」として紹介された「埴輪(はにわ)」。世界との交流の中でどのようにはぐくまれてきたのでしょうか?
-
昭和のくらし博物館 今年は「昭和100年」ですが、昭和のくらし博物館は、1951(昭和26)年に建った住宅です。私たち小泉家の住まいで、往時の家財道具ごと保存しています。主に昭和30年代から40年代半ばのくらしを感じられるようにしています。この時代は、日本人が最も幸福だったと思います。日本が戦争をしない国になり、戦後の混乱期から何とか立ち直り、明るい未来が見えてきた時代でした。
-
国立国際美術館 既製品の中にある織物の歴史や先人の営みを参照し、吟味し、手を加えることで、誰も見たことのないような作品が生まれています。
新着コラム
-
グッとグルメ 羽田美智子さん 吉祥寺MATSUHIRO 吉祥弁当 私が主演する舞台のときに差し入れたら、グルメな先輩たちが「みっちゃん、今日のお弁当、最高!」なんて口々に言ってくださったんです。私の勝負弁当の一つなんです。
-
グッとグルメ 横尾初喜さん
レストラン蜂の家 ビーフシチューとハンバーグ煮込み 映画監督の横尾初喜さん。出身地である長崎県佐世保市のお店で食べる「ビーフシチューとハンバーグ煮込み」が撮影の支えだそうです。 -
-