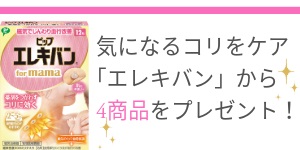-
「有馬人形筆」 筆先を下にして持つと、筆の尻からひょっこり豆人形が顔を出す。筆を逆さにすると人形は姿を隠してしまう。神戸・有馬温泉に伝わる兵庫県の伝統的工芸品「有馬人形筆」だ。
2018/06/27 更新
-
「神農の虎」 ユニークな表情をした動物の張り子や愛らしい土人形、色鮮やかな凧(たこ)など、日本各地に伝わる郷土玩具。本展では、戦後に作られた所蔵品から約550点が府県別に並ぶ。
2018/06/20 更新
-
「都鄙秋興」 縮れた葉、牡丹(ぼたん)のように折り重なった花びら。突然変異が生み出す「変化朝顔」は江戸の文化文政期(1804~30)、熱心な愛好家らの手で広がり、珍重さを競う品評会も催された。
2018/06/06 更新
-
「緑色のテーブルの上の静物」 仏の近代絵画、フォービスム(野獣派)の巨匠モーリス・ド・ヴラマンク(1876~1958)。本展では、彼の第二期ともいえる「セザニアン期」から最晩年までの作品76点を時代を追って展示する。
2018/05/09 更新
-
「霊峰春色」/「東海神秀」 今回は横山大観(1868~1958)の「霊峰春色」と、橋本関雪(1883~1945)の「東海神秀」の富士山対決。いずれも第2次大戦前、国威発揚のために描かれたという。
2018/05/01 更新