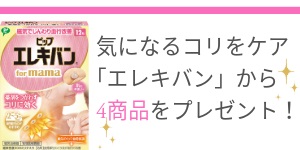名古屋市美術館
共存する生と死 壁画的に描く

静岡県生まれの画家北川民次(1894~1989)は20代でメキシコに渡り、「メキシコ・ルネサンス」と呼ばれる美術運動に大きな影響を受けました。当館は、1936年に帰国後の北川が名古屋市や愛知県瀬戸市で活動した縁から、作品211点を所蔵。関連してメキシコ近代美術約630点をコレクションの柱としています。
「メキシコ・ルネサンス」は独裁政権が倒れた革命後の1920~30年代に興った芸術・文化運動です。その中心となったのが、人々にメキシコの伝統や歴史、革命の意義を伝えるため公共の場に描かれた壁画運動でした。北川は約15年間のメキシコ滞在中、運動を牽引した画家ディエゴ・リベラ(1886~1957)らと交流しました。
「トラルパム霊園のお祭り」は、首都近郊トラルパンの野外美術学校で児童美術教育に携わった時期に描かれました。右手前に幼子を抱く女性、左側からは子どもの棺おけを掲げた葬列が進み、その先には霊園が。ジグザグに視線を導く仕掛けが秀逸です。
時間や場所が様々な出来事をパッチワークのように構成した画面は、壁画運動の影響を色濃く感じます。生と死のモチーフの共存は、死を生と近しいもの、新しい命に生まれ変わる過程ととらえるメキシコの死生観とつながります。
リベラの妻フリーダ・カーロ(1907~54)の「死の仮面を被った少女」のモチーフにもそうした死生観が反映されています。骸骨の仮面とマリーゴールドの花は、死者の魂を迎える「死者の日」の祭りに用いられるもの。自伝的な絵画を多く残したカーロは流産で失ったわが子をイメージして少女を描いたとも考えられ、様々な想像を促す作品です。
(聞き手・木谷恵吏)
《名古屋市美術館》 名古屋市中区栄2の17の25(問い合わせは052・212・0001)。[前]9時半~[後]5時(入館は30分前まで)。2点は11月27日まで常設展示。300円。原則[月]休み。28日~2023年4月14日は工事のため休館。

学芸員 勝田琴絵 かつた・ことえ 慶応義塾大学大学院修了。国立新美術館研究補佐員を経て2020年から現職。メキシコ近代美術や現代美術を担当。 |
私のイチオシコレクションの新着記事
-
京都国立博物館 中国・唐と日本の技術を掛け合わせた陶器「三彩蔵骨器」。世界に日本美術を体系的にアピールするため、「彫刻」として紹介された「埴輪(はにわ)」。世界との交流の中でどのようにはぐくまれてきたのでしょうか?
-
昭和のくらし博物館 今年は「昭和100年」ですが、昭和のくらし博物館は、1951(昭和26)年に建った住宅です。私たち小泉家の住まいで、往時の家財道具ごと保存しています。主に昭和30年代から40年代半ばのくらしを感じられるようにしています。この時代は、日本人が最も幸福だったと思います。日本が戦争をしない国になり、戦後の混乱期から何とか立ち直り、明るい未来が見えてきた時代でした。
-
国立国際美術館 既製品の中にある織物の歴史や先人の営みを参照し、吟味し、手を加えることで、誰も見たことのないような作品が生まれています。
-
滋賀県立美術館 画面を埋め尽くす幾何学模様の正体は……。人に見せるためにかかれたのではない、アートが発する魅力。
新着コラム
-
-
-
グッとグルメ すとぷり 莉犬さん
吉祥寺コーンバレー オマージュコース~炎と少女~ すとぷりの莉犬さんはジブリ映画好き。特にお気に入りの「ハウルの動く城」に登場するベーコンエッグや、ジブリ作品にはおなじみのマックロクロスケ風のデザートにこころはわしづかみ。 -