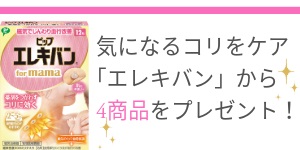妖精の森ガラス美術館
ウランが発光 皇帝を魅了

当館がある岡山県鏡野町の人形峠ではかつて天然ウランが採掘されました。採掘終了後、新しい地域特産品として「ウランガラス」開発計画が持ち上がり、当館は2006年に制作と展示の拠点としてオープンしました。
着色剤として微量のウランを混ぜたウランガラスは1830年代にボヘミア(チェコ)で生産が始まりました。明るい黄色みを帯び、強い紫外線を当てると緑色に発光する美しさが人気を呼び、欧州各国や米国に広まりました。日本でも大正から昭和初期に食器や酒器などが作られました。
「ロシア皇帝のゴブレット(脚付杯)」はウランガラスの素地全面にエナメル彩で植物の模様が描かれています。8脚のうち2脚の底にはロシア帝国の国章と当時のロシアで最大だったクリスタル工場の名が刻印されています。
ロシアではウランガラス発明から間もない1850年ごろ、皇帝が製造技術や原料をボヘミアやフランスから輸入し、国内の工場で製造させたことがわかっています。紫外線ライトが一般的でなかった当時はこれほどの緑色が見られる機会は少なかったはずですが、緑がかっていく色みの変化を楽しんでいたのではないでしょうか。
現代の作品「杯」は、日本を代表するガラス作家の内田守と当館工房スタッフの日浦佑記の共同で、約2カ月かけて制作されました。確かなカット技術によって光が杯の内側で乱反射し、特有の緑色がより美しく幻想的な表情を見せます。
ウランというと「怖いもの」という印象がありますが、ウランガラスに含まれるウランはごく微量です。日常生活に用いても問題ありません。
(聞き手・片野美羽)
《妖精の森ガラス美術館》 岡山県鏡野町上斎原666の5(問い合わせは0868・44・7888)。午前9時半~午後5時(入館は30分前まで)。500円。原則(火)、年末年始休み。

学芸員兼工房スタッフ 三浦和 さん みうら・ひとし 倉敷芸術科学大で吹きガラスと出会う。千葉県、静岡県のガラス工房勤務を経て2017年から現職。 |
私のイチオシコレクションの新着記事
-
京都国立博物館 中国・唐と日本の技術を掛け合わせた陶器「三彩蔵骨器」。世界に日本美術を体系的にアピールするため、「彫刻」として紹介された「埴輪(はにわ)」。世界との交流の中でどのようにはぐくまれてきたのでしょうか?
-
昭和のくらし博物館 今年は「昭和100年」ですが、昭和のくらし博物館は、1951(昭和26)年に建った住宅です。私たち小泉家の住まいで、往時の家財道具ごと保存しています。主に昭和30年代から40年代半ばのくらしを感じられるようにしています。この時代は、日本人が最も幸福だったと思います。日本が戦争をしない国になり、戦後の混乱期から何とか立ち直り、明るい未来が見えてきた時代でした。
-
国立国際美術館 既製品の中にある織物の歴史や先人の営みを参照し、吟味し、手を加えることで、誰も見たことのないような作品が生まれています。
-
滋賀県立美術館 画面を埋め尽くす幾何学模様の正体は……。人に見せるためにかかれたのではない、アートが発する魅力。
新着コラム
-
-
-
グッとグルメ すとぷり 莉犬さん
吉祥寺コーンバレー オマージュコース~炎と少女~ すとぷりの莉犬さんはジブリ映画好き。特にお気に入りの「ハウルの動く城」に登場するベーコンエッグや、ジブリ作品にはおなじみのマックロクロスケ風のデザートにこころはわしづかみ。 -