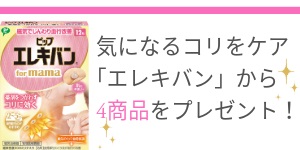鎌倉市鏑木清方記念美術館
江戸趣味映す 妻への留め袖

当館は美人画で知られる日本画家・鏑木清方(1878~1972)が晩年を過ごした旧宅跡地に1998年に開館。門や画室は当時の様子を再現しています。
清方が描いた女性はほとんど着物姿です。駆け出しの挿絵画家だったころ、収入を補うために浴衣地の図案を作る仕事もしていた清方は、画中の人物の着物に、自ら考案した柄を緻密(ちみつ)に描きました。
身内の浴衣や手ぬぐいなどの意匠を手がけることもあり、「絽地扇面描絵柄江戸褄(ろじせんめんかきえがらえどづま)」は妻・照(てる)にあつらえた留め袖です。柄はすそだけにあり、そのほかは無地。一見すると素っ気ないようにも感じます。
ところが、照が着た姿を写した写真では印象がガラリと変わります。椅子に座った照のひざ下を、風に舞うような涼しげな扇が飾ります。みずみずしいグラデーションといい、女性を観察し尽くした清方ならではの絶妙な配置を感じます。
扇面のリンドウやナデシコ、ヤブランなど秋を先取りした花は絵筆で描かれています。閉じた扇子が一つ、目を留めさせるポイントを置いているのが心憎いですね。全体に派手ではなく、東京で生まれ育った清方の洗練された江戸趣味が表れています。
清方は絵の中に市井の情景や風俗を残そうとしました。自らの作品を美人画と呼ばれるのを好まず、庶民の生活を描く「社会画」と自負していたこともありました。
うちわ「のれん」に描いたのも日常の何げない一コマ。のれん越しに「ちょいとあなた」とでも呼びかける声が聞こえてきそうです。
(聞き手・斉藤由夏)
《鎌倉市鏑木清方記念美術館》 神奈川県鎌倉市雪ノ下1の5の25(問い合わせは0467・23・6405)。300円(特別展は450円)。月(祝の場合は翌平日)、展示替え期間など休み。2点は9月11日まで展示。

学芸員 今西彩子 いまにし・あやこ 2010年から現職。開催中の企画展「夏から秋へ 季節のよそおい」ほか、日本画や多色摺(ず)り木版画ワークショップなども担当。 |
私のイチオシコレクションの新着記事
-
京都国立博物館 中国・唐と日本の技術を掛け合わせた陶器「三彩蔵骨器」。世界に日本美術を体系的にアピールするため、「彫刻」として紹介された「埴輪(はにわ)」。世界との交流の中でどのようにはぐくまれてきたのでしょうか?
-
昭和のくらし博物館 今年は「昭和100年」ですが、昭和のくらし博物館は、1951(昭和26)年に建った住宅です。私たち小泉家の住まいで、往時の家財道具ごと保存しています。主に昭和30年代から40年代半ばのくらしを感じられるようにしています。この時代は、日本人が最も幸福だったと思います。日本が戦争をしない国になり、戦後の混乱期から何とか立ち直り、明るい未来が見えてきた時代でした。
-
国立国際美術館 既製品の中にある織物の歴史や先人の営みを参照し、吟味し、手を加えることで、誰も見たことのないような作品が生まれています。
-
滋賀県立美術館 画面を埋め尽くす幾何学模様の正体は……。人に見せるためにかかれたのではない、アートが発する魅力。
新着コラム
-
-
-
グッとグルメ すとぷり 莉犬さん
吉祥寺コーンバレー オマージュコース~炎と少女~ すとぷりの莉犬さんはジブリ映画好き。特にお気に入りの「ハウルの動く城」に登場するベーコンエッグや、ジブリ作品にはおなじみのマックロクロスケ風のデザートにこころはわしづかみ。 -