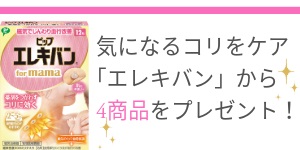吉祥寺コーンバレー オマージュコース~炎と少女~ すとぷりの莉犬さんはジブリ映画好き。特にお気に入りの「ハウルの動く城」に登場するベーコンエッグや、ジブリ作品にはおなじみのマックロクロスケ風のデザートにこころはわしづかみ。

【SP】”まよパン”作者の好きなパン
大沼紀子さんロングインタビュー

2005年に「ゆくとし くるとし」で第9回坊っちゃん文学賞大賞を受賞し、小説家デビューを果たした大沼紀子さん。作品は「食べ物」が題材になっていることも多く、おいしそうな状況描写は読んでいると自然にお腹がすいてきます。紹介いただいたパンのお話はもちろん、大沼先生の食べ物に関する執着や小説にでてくるキャラクターの考え方など…「グッとグルメ」コラムに収めきれなかったお話をお届けします。(聞き手・中山幸穂)
※大沼紀子さんは11月30日(木)朝日新聞夕刊「グッとグルメ」に登場しました。
――今回ご紹介いただいたのは大沼さんの地元、岐阜・高山のパン屋「トランブルー」のパン。このお店はどのように知ったのですか?
若い頃、知り合いから聞いたのがきっかけです。はじめは親が買ってきてくれました。高山の食べ物は、おじいちゃんおばあちゃんが好みそうな雰囲気のものが多いと感じていたのですが、急にトランブルーっていうおいしいパン屋さんがあるよと聞いて、自分でも実際に行ってみて入ったときの見た目に圧倒されました。
――ショーケースにパンがずらっと並んでいて圧巻ですよね。
すごくキラキラしたパン屋さんだと感じました。まるで服屋さんやジュエリーショップに入ったときみたいなどこか華やぐような楽しさがあって。素敵なところに来たみたいなワクワク感を感じながら、パンが買えるというのが結構新鮮な体験だったんです。
――そこから通い出した?
そうですね。私のなかではおいしい地元のパン屋だと思っていたのですが、帰ってくる度に有名になっていっている感覚があります。「真夜中のパン屋さん」を書いていた時はパン屋さんに取材に行ったりもしたので、そこで「近所にトランブルーというパン屋さんがあって…」という話をしたら「知ってる、すごいよね」みたいな反応をいただくことが多くて、やっぱりおいしいんだ、とすごくうれしく思いました。地元のものが褒められると、自分のことじゃないのに妙に嬉しくなるものなんですね。
――たくさんある種類から選んでくださったのは「大納言」。どんなパンか教えていただけますか。
どちらかというとハード系の生地感のあるパンです。トランブルーで販売しているTバゲットと似ているけれど、中身の生地が少し違う気がします。表面がすごくパリッとしていて、でも中はふわっとやわらかい。ぱりっと感とやわらかさが混ざる感じがいいですね。かみごたえもあるので、かむほどに楽しい感じ。小麦の味と表面のちょっと焦げた感じの味も香ばしさを引き立てていて絶妙です。そこに、小豆のほどよい絶妙な甘さがプラスされて、いくらでも食べられる味なんです。お店いかれたんですよね?
――行きました。大納言以外にも色んな種類がありどれも魅力的でした。
きらびやかなパンとかもいっぱいあるじゃないですか。デニッシュとか結構ケーキみたいで美しいし。その中だと素朴な感じもあったりしますが、そこが落ち着きます。他のパンは毎回とかではないですが、これだけは欠かさず買ってしまいます。母も好きなので、「トランブルー行くけど何か買ってくる?」と聞くと、「大納言」みたいなやりとりもあります。
――母娘そろってお好きなのですね。
なんだろう。年をとってくるといいんですかね(笑)。クロワッサンとかが好きだった時期もあるんですよ。だからもっと年をとったらまた好きなパンが変わるかもしれない。今現時点はこれがいいですね。
あんぱんとはまた全然違ってハード系のパンであるところもよいし、甘さも「あまあま」というよりは、ほんのりみたいな。甘すぎるとやっぱりどうしても「もういいかな」ってなるんですが、ちょうどいい。この感じが毎回食べてしまう理由なのかもしれないですね。
追加でバターなどをのせるとまたしょっぱさも出て、甘じょっぱい感じがたまりません。普通のバゲットにあんことバターを挟んだパンも大好きなんです。あずきとパンは組み合わせとして最高だと思います。
――買ったパンを召し上がられるのは朝が多いですか?
そうですね。昼も全然食べますけど、朝おいしいパンを用意しておくと、ちょっといい気持ちで寝られるし、朝もいい一日が始められる気がします。だからなるべくおいしいパンを食べたいと思っています。
――じゃあ朝はパン派?
パン派です。というか実はお米食べないんですよ。
――夜もですか?
はい。もう年だし食べなくていいんじゃないと思っておかずだけ準備しています。そう言うと驚かれることが多いんですけど。私としては、みんながそんなにお米を食べていることのほうにいつも驚いています(笑)。
――すこしお話は変わりますが、これまでに大沼先生が書かれた小説には食べ物が多く登場します。細かな描写が読んでいて非常に食欲をそそられるのですが、描写されるときに意識していることはありますか?
意識とまではいきませんが書くときは実際に食べたときの記憶を思い出しながら書いています。自分ではあんまり食べることに執着はない方だと思っていたんですよ。食べることが大事とも楽しいとも思ってなかったんですけど…よく考えてみたら意外と執着があるのではないかとも思ってきました。
――どんなところに執着があると?
子どもの頃、ドリアをはじめて食べておいしさに感動したんです。でも親に言ってもなかなかわかってもらえなかった。けれどどうしてももう一度食べたいから、本を買ってもらって自分で作ったりとか。
もうひとつ、私が幼い頃おじいちゃんとおばあちゃんが五平餅のお店をやっていて、1から自分たちでつくっていく様子をよく見ていたんです。だからかはわかりませんが、この人は丁寧な仕事をしているはずみたいなことが、食べた時に伝わってくることがあって。手間をかけている様子が見えたり想像したりするのが好きなんだろうなっていうのは最近気がつきました。
――そういった幼い頃の経験が執筆にもつながっているのでしょうか。
そうかもしれない。手間ひまがかかった食べ物を求めている傾向はあると感じます。手間暇をかける=美味しいになるわけではないとは思うんですけど、その過程が味に出てきてしまう部分は否めないよなって思います。その思いから書く時に「ねちねち」書いてしまうのだろうなと。ちょっと楽しくなっちゃって。行数増えちゃうのになとは思うんですけど(笑)。
――小説に登場するキャラクターは何かを抱えていて、完全に乗り越えるという訳じゃないけれど、少しずつ前を向いていく、そんな人が多いと感じます。いつもキャラクターはどのように考えられているのでしょうか。
あんまり考えてないと言ったら変なんですけど、特殊なことをしようって思っているわけではないです。
うーん…、昔はなんで私はこんなに苦しいのと思っていたんです。でもこれが普通だ、幸せそうに見えるあの人だってそういう顔をしているだけだって思い込んで乗り越えたんですね。そういう風に思ってしまっていたところがキャラクターにも反映されたのかなと思います。
――「真夜中のパン屋さん」では「パンは一人で食べても二人で食べても美味しいままだろう」というせりふなど、どんな人も優しく包んでくれるような言葉が多く心に残っています。
よく二人で食べると一人で食べるより美味しいよねとか一人で何かをするより二人でやった方がっていうことを言われがちですが、私はそれが若い頃しんどかったんですよね。どうしても一人でやってしまうことが多くて、二人で何かをやる喜びとか、家族で何かをやる喜びって言うのがわからなくて。私はそれでも一人でいられることを楽しめるし幸せだし、それの何が悪いんだみたいな思いを思春期とかに強く抱えていたんですけど、段々ひとりに固執する必要がないんだなっていうのが分かってきて言いたくなったのだと思います。そういう思いが誰かに響いていたらすごくありがたいです。
大沼紀子
脚本家・小説家。1975年、岐阜県出身。ドラマ化もされた「真夜中のパン屋さん」シリーズで注目を集める。 他の著作に『ばら色タイムカプセル』『てのひらの父』『空ちゃんの幸せな食卓』(ポプラ社)『路地裏のほたる食堂』(講談社)など。
グッとグルメの新着記事
-
すとぷり 莉犬さん
吉祥寺コーンバレー オマージュコース~炎と少女~ すとぷりの莉犬さんはジブリ映画好き。特にお気に入りの「ハウルの動く城」に登場するベーコンエッグや、ジブリ作品にはおなじみのマックロクロスケ風のデザートにこころはわしづかみ。 -
すとぷり ジェルさん
スガキヤ ラーメン 「こんなに安くておいしいラーメンがあるのかと!」 すとぷりのジェルさんが子どもの頃から好きだった味と、地元・大阪の家族の思い出。 -
坂本美雨さん
中国屋台十八番 新川店「チャーハン」 お店のチームワークを象味。仕事仲間との絆も深まる味。 -
梶芽衣子さん
御料理 花ぶさ 生芝海老揚しんじょう 梶芽衣子さんの「グッとグルメ」は、御料理 花ぶさ 生芝海老揚しんじょう