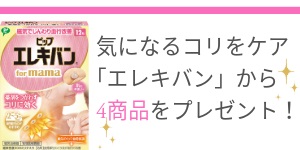浪曲づくりは旅の記憶をたよりに

2月、3月、4月。旅がありませんでした。珍しい。
浪曲というのは、全国津々浦々、旅巡業のなかで発展してきた芸能だ、と私は思っています。一カ所にとどまっている芸ではなく、旅から旅へ、さまざまな地域の方々の前で、様々な土地の物語を語るもの。都市に限定されない、芸能だと思っている。
それなのに、旅が、ない。元気がいまひとつ、出ない。
だから「旅日記」はお休みね~、と許してもらうわけにはいかず。
年が明けてから、新作づくり、また、しばらく演じていない演目を蔵から引っ張り出してやらねばならないこともあり、演目を制作し、必死で覚える(だいたい30分尺のもので、6000字くらい、の文章量です)。そして節付けをして、稽古に追われる日々です。
せめて、ネタのなかで旅をしよう。そして過去の旅の記憶をネタに生かしていく。
年明けに挑んだのは、三遊亭白鳥師匠の新作落語「鉄砲のお熊」の浪曲化。この作品は、熱海と小田原の間にある「月影村」という架空の村が舞台です。

浪曲「鉄砲のお熊」を初披露した演芸会のちらし
私は横浜市の出身。湘南の地は、なじみ深い。
私の祖母は仕立屋をしており、婚礼衣装など、けっこう高級な着物の仕立ても請け負っていたようです。朝から晩まで、「ばいた」(仕立物をするときの作業台)の前に座っていました、夜どおし仕事をして仕上げた着物を、平塚の百貨店「十字屋」に納めに行く。
祖母は、まだ学校にも上がってなかった小さい私を、よく連れていってくれたのです。おばあちゃんと東海道線に乗って平塚に行く。行きは、ふつう車両に乗っていく。帰り、たぶん祖母はその場で仕立て代をいただいたんでしょう、夜なべして疲れ切った体を休めるためか、グリーン車。祖母はうとうと眠っていました。私もグリーン車で帰る。電車から見える、町の風景。
また、とある夏。父が鎌倉の由比ガ浜で海の家を開き、家族で過ごしたことがありました。泳ぎの達人の祖父に、足が届かないような深いところまで連れていかれて、海に放り出されておぼれそうになった。ひどい祖父だったなあ。そのときがぶがぶ飲み込むことになった海水の味。

1980年代の由比ガ浜
たまに父親が、車を出してくれて箱根までドライブ、なんていうこともあったなあ。車で箱根の山道を上がっていくと、随所に滝があってわくわくしました。私の滝好きはあのころに養われたのかもしれない。
鎌倉や茅ヶ崎、馬入川を渡れば平塚、そして小田原、湘南の景色。陽の光。海辺の町の光景。風の匂い。そして天下の険たる箱根の山の風景。「鉄砲のお熊」の台本を書きながら、物語の場面場面で、記憶にある匂いや景色を思い出し、それらを必要に応じ、文章に埋め込みながら作っていきます。
浪曲は物語を語るものだけれど、描きたいのは筋だけではない。景色、色、匂い、肌触り、味……、そういう感覚的なものを書き込んで埋め込んで、それを無意識的にでも感じてもらえるように作りたい、と常々思っています。
先月作ったのは「瘋癲売茶翁(ふうてんばいさおう)」というオリジナルの新作。江戸時代に実在した、煎茶の中興の祖と言われている売茶翁と呼ばれた人を扱った浪曲です。

開催中の相国寺展で伊藤若冲が描いた売茶翁の絵が見られる
佐賀に生まれ、幼いころから禅の修行を積み、佐賀蓮池藩菩提寺の住職となるはずの道を捨てて、還俗して京都の路上へ。茶を淹れ、わずかな銭をもらって暮らすようになった。
私は日本茶が好きです。好きが高じて、日本茶セミナーに通ったり、台湾にお茶づくりに行ったり。徳島県の山奥の村で茶摘みのアルバイトをしたことがあります。甘くも辛くもない「お茶」というものが、世界中で珍重され飲まれ続けているのはなぜか、お茶を飲む時間がとても豊かに感じられるのはなぜか、という問いが自分の中にずっとあり、それを、この人の生き方に託して、物語にしてみたかった。
売茶翁の活躍の舞台は京都です。
京都大好き!!! 何度も足を運んでいるけど、ヒマさえあれば、京都に行きたい。売茶翁が茶道具をかついで店を広げていたのは、東福寺の通天橋の下、糺の森、東山の湧き水のそば。江戸時代の風景はわからないけれど、私は旅行をしてその場所に行ったことがある。記憶をたぐりながら、売茶翁が水を汲む場所の緑豊かな風景が見えるように、清冽な流れが感じられるように、作りたい。

京都・東福寺の通天橋
お茶を飲む時間の豊かさは、茶を淹れる過程にもあるはず。お湯を沸かすために火をおこす。火を炊く香り。湯の沸く音。売茶翁が道具を扱う作業の流れるような美しさ、整えられた茶道具、お茶の葉が開くのを待つ時間、そして茶碗に注ぐ様子。それが感じられるように作りたい、と思うわけです。
台本制作、難しい。
意味や筋を伝えることも大事だけれど、一席30分の物語を聴いて、お客さんも一緒に物語を旅した気持ちになってもらえたら。物語を聴きながら、きれいだな、美しいな、気持ちいいな、まぶしいな、丁寧なことはいいことだな、などなど、五感が活性化されるような浪曲でありたい、そんなふうに作りたい。
そしてそこに、人がいる。たかが浪曲の、その中に出てくる人物の、その実在感。それが一番難しい。浪曲の登場人物が、風景の中にすっくと立ちあがり、表情や感情や息遣いが感じられる。どんなふうに生きているのか、感じられる。その物語を聴いたあと、お客さんがわが身を振り返り、今日も生きてみよう、暮らしてみようと、ちょっと元気になってもらえる浪曲を演じたい。
売茶翁は、奇想の画家といわれる伊藤若冲と深く交流しました。演じるにあたり、若冲の絵を観に行きました。有名な「動植綵絵」。描かれた植物と鳥の生命力が、むん、と迫ってくるような絵です。200年前に描かれた絵から、強く伝わってくる生命力。

伊藤若冲の「動植綵絵 薔薇小禽図」
浪曲で、それをやりたいのです。筋立てや意味を上回る、なにか。
問われているのは、私の力だ。
◆たまがわ・ななふく 横浜市出身。筑摩書房の編集者だった1995年、曲師(三味線弾き)として二代目玉川福太郎に入門。師の勧めで浪曲も始め、2001年に浪曲師として初舞台。古典から自作の新作まで幅広く公演するほか、さまざまな浪曲イベントをプロデュースし、他ジャンルの芸能・音楽との交流も積極的に取り組む。2018年度文化庁文化交流使としてイタリアやオーストリア、ポーランド、キルギスなど7カ国を巡ったほか、中国、韓国、アメリカでも浪曲を披露している。第11回伊丹十三賞を受賞。7月19日と20日、東京・銀座の観世能楽堂で独演会を開催。


◆「ななふく浪曲旅日記」は毎月第三土曜に配信します。
ななふく浪曲旅日記の新着記事
-
お家芸の生まれ故郷、東庄町へ 浪曲師の玉川奈々福さんが受け継ぐ玉川一門の家の芸に「天保水滸伝」があります。物語の舞台となっている千葉県東庄町は奈々福さんにとって第二の故郷です。
-
太福さんが末広亭でトリをつとめ大盛況 浪曲界に一大事件 玉川太福さんが落語の殿堂、新宿末広亭で10日間トリをつとめ、しかも連日大入り。浪曲界、いや演芸界に一大事件が起こった1月です。
-
大衆演劇との奇縁で実現した「節劇(ふしげき)」 かつて大衆演劇の追っかけをしていた玉川奈々福さん。数十年ぶりの再会が「節劇」という浪曲と大衆演劇とのコラボレーションを実現させました。
-
子どもたちのきらきらした目に感動 11月は旅から旅だった浪曲師の玉川奈々福さん。静岡で小学生に浪曲の実演とワークショップを開いたのですが……。