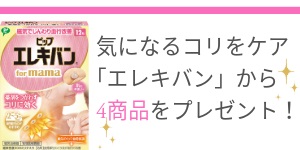-
「呼ぶ」 伊勢神宮に奉納された作品は神宮美術館に所蔵されるものの、あくまで神への献納品。「当館に納められること自体が、祈りの行為に基づきます」と学芸員の瀬戸裕子さんは話す。
2020/01/07 更新
-
「紬織(つむぎおり)着物 青垣」 植物染料にこだわった紬織を手がける人間国宝の染織家、志村ふくみ(95)。「自然への畏敬の念を持ちながら制作する姿勢は祈りそのもの」と学芸員の瀬戸裕子さんは話す。
2019/12/24 更新
-
「ゴリアテの首を持つダヴィデ」 人々の感情を揺さぶる生々しい表現で名声を博したイタリアの画家カラバッジョは、斬首をモチーフにした作品が多い。ついには本作で自身の生首を描いた。
2019/11/19 更新
-
「法悦のマグダラのマリア」 イタリア絵画の巨匠カラバッジョ(1571~1610)は、作品も人生も劇的なことで知られる。気性が荒く暴力事件を何度も起こした末、1606年に1人の男を刺殺。
2019/11/12 更新
-
「リュート弾き」 16世紀末のイタリアに現れた天才画家カラバッジョ(1571~1610)。本展は、光と影の描写と生々しい写実表現でローマに衝撃を与えたカラバッジョ作品約10点と、その影響を受けた画家たちの作品約30点で構成する。
2019/11/05 更新
-
「アリバロ尖底壷」 15~16世紀にかけて、南米で栄えたインカ帝国。高度な農耕、土木技術を持ち、空中都市と呼ばれるマチュピチュのような高地でも、灌漑用水路や段々畑を活用して農業を営んでいた。
2019/09/24 更新