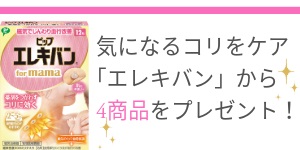太福さんが末広亭でトリをつとめ大盛況 浪曲界に一大事件

1月に起きた事件のリポート、現場からの報告です。
事件の発端は、昨年末の新宿末広亭。
出演していた弟弟子の玉川太福(だいふく)さんが、新宿末広亭一月下席夜の部で主任を務める、と高座で発表しました。

私は一般社団法人日本浪曲協会所属の浪曲師ですが、昨年春より後輩の広沢菊春、国本はる乃とともに、公益社団法人落語芸術協会にも入会させていただきました。こちらに入ると、都内の寄席である新宿末広亭、池袋演芸場、浅草演芸ホールに顔付けていただくことができます。
太福さんは、2007年に玉川福太郎に入門した私の弟弟子です。
意欲的に新作に取り組み、臆面もない大音声で物語る浪曲という芸で超マイクロな日常を唸(うな)る、そのギャップが生み出す笑いで大変な人気を得て、いち早く落語芸術協会からお声がかかり、6年半前に入会、積極的に寄席に出演していました。
人気ものは超忙しい。見てくださいこの出演予定。
太福さんのWebサイトの「3・4月のざっくり予定ぃぃぃ」(https://tamagawadaifuku.tokyo/news/202503-4/)
でも、ちょっとでもスケジュールが空いてると、彼は寄席の出番を入れてしまうのです。寄席が好きなんだなあ。
それにしても。
入会してまだ10年も経たない「浪曲」が、落語の定席である末広亭で10日間トリをとることを任されたとは! 浪曲師が落語の席で主任を務めるのは、昭和39年に亡くなった二代目広沢菊春先生以来60年以上ぶりらしく。
とにかく、びっくりした。とにかく、嬉しかった。
が、同時にちょびっと心配でもあった。彼は人気者ではあるけれど、浪曲が主任の公演にお客さんは来てくれるだろうか。
浪曲の定席、浅草の木馬亭はキャパ131席。毎月1日から7日まで公演していますが、たとえトリが太福さんであっても満席御礼になることは、残念なことにそんなにない。末広亭は1階と桟敷、2階があってキャパは313席。
新宿末広亭は、実は浪曲と深いかかわりがあります。
明治のころの創業で、明治末期に浪曲師の末広亭清風が買い取り、浪曲寄席として経営を始めました。のちに落語の寄席になったそうですが、第二次世界大戦で焼失したところを、戦後、現在の北村会長、真山社長の祖父に当たる銀太郎氏によって再建され、いまに継承されています。木造の、昭和の香り満ちる建物もとても素敵。正面の提灯に灯りがともり、路地を照らす風景は、なんともなつかしく嬉しい。新宿区の地域文化財に指定されています。

弟弟子の晴れ舞台、なるべく出演したいと10日間のうち5日出させていただくことになりました。そして、ちょびっとでも盛り立てたくSNSで発信する。


10日間の顔付けが、これまたすごい。
落語芸術協会の若手スターが歴々と並ぶ顔付け。重鎮の師匠が仲入り、ヒザ前(トリの前の前)に、そしてヒザ(トリの前)にはベテランの色物の師匠が出てくださっている。

弟弟子の初主任公演に、こんな方々が出演してくださるのだ。
1月21日が初日。私の出演日ではないけれど、心配でSNSの反応をチェックする。すると!!!




え?え?ほんと?
そして2日目、22日。奈々福は初日です。
木戸にご挨拶にうかがうと「玉川太福さんへ」と染め抜かれた新しい幟(のぼり)が2本、夕空にはためいている。「夜の部主任 玉川太福」という寄席文字の看板がでかでかと掲げられている。

この日は、落語芸術協会副会長の春風亭柳橋師匠の代演で、神田伯山先生ご出演。
私の出番は18時。楽屋入り17時。
入ってみて驚いた。
その時点で2階までお客さんがいっぱい入っている!
そして舞台にも、そして客席後ろにもお祝いのお花がいっぱい。太福さんの人徳だ……、じ~んとします。そして、ちょびっとうらやましい。
最終的にお立見の出る超満員でした。
私は仲入りで物販にも駆り出され、ちょうど出たばかりの太福さんの著書(またなんといいタイミングで本が出るのよ……)「私浪曲 唸る身辺雑記」(竹書房)を売りました。これが飛ぶように、まさに飛ぶように売れる。50冊が仲入りで完売!

トリの太福さん。
いつもの寄席は落語や色物の間に浪曲が入る。流れを途切れさせぬよう、浪曲も講談と同じ形で、講釈台を置いて座って演じます。でもさすがは末広亭、なんと浪曲の演台があるとのこと。いつもは前座さんたちの荷物置きになっているとのこと(笑)。
それを引っ張り出して、本来の舞台スタイルでやるということで、一旦幕を下ろし、舞台転換をします。
幕が上がるや「待ってました!」「たっぷり!」の掛け声、万雷の拍手。
末広亭の天井から、きらきらと銀粉が降ってくるような祝祭感。
こんな日に、彼はなにかけるんだろう。
あれかな、あれかなと想像しつつ、どきどきしながら聴いていた。
そして彼がこの日かけたのは……。玉川の家の芸である「天保水滸伝(てんぽうすいこでん)」の中から、その白眉である「笹川の花会」。大ネタではありますが、連続モノの一席だし、正直、寄席で受けるような笑いのある演目ではない。
でも、これをかけることに太福さんの覚悟を感じたのです。

舞台袖で弟弟子の一席に耳を傾ける 撮影:瀧川鯉八
そうか、そうなんだね。
曲師は、うちの師匠、故・玉川福太郎の妻であり、入門以来、太福さんの曲師を務めてこられた玉川みね子師匠。
寄席ではあまり出さない侠客ものの一席、客席がしんと静まり返り、熱を持って聴いてくれているのがわかる。
終わって、太福さんとみね子師匠が深々と頭を下げる。

これは座り高座のときの写真。いずれも深々と……
幕が下りる。
鳴りやまない拍手。
カーテンコール。
最後は、出演者みな舞台に上がって、伯山先生の音頭で三本締め。お客さんたちの笑顔。こんな風景が見られるとは。
しかし、油断してはいけないのだ。
この日は伯山先生がご出演だったことも集客に寄与しているだろう。勝負は3日目から。この日の浪曲は国本はる乃の出演。
やはり立ち見の出る盛況だったらしい。そして、この状況を、ご出演の方々が、ご来場のお客さんが、ものすごく喜んでおられるのが、楽屋の様子やSNSの投稿からうかがえる。
24日、25日、28日、30日と出演させていただいた。
楽屋の連携がすばらしい。主任を盛り上げる流れをつくる。
そして日を追うごとに、客席の祝祭感、太福さんを祝う気持ちが盛り上がっていく。いったいどういう場になっているのかと、後輩芸人たちが「勉強させてください!」と楽屋にやってきて、ただでさえ狭い末広亭の楽屋がぎゅうぎゅうになる。
そしてこの場にいられる特別感を、客席にいるお客さんも、楽屋の芸人たちもしみじみと味わっている感じがする。
真山社長が楽屋に来られる。「初席超えだよ」
私はまだ入ったばかりで落語の寄席のことはよくわからないが、浪曲定席木馬亭でも、お正月興行はお客さんがよく入る稼ぎ時。その初席の入場者数を早々に超えたらしい。
「えええええええっ!」。楽屋一同の驚きの声。
「えええええええっ?」。それに追随してみる。
太福さんの弟子のわ太(だい)、き太(だい)。嬉しいだろうなあ、誇らしいだろうなあ、一生懸命働いちゃうだろうなあ。
楽日。早々に札止め。
御趣向で私は開口一番のき太さんの曲師を務めさせていただきました。幕が上がったときの客席のどよめきが嬉しかったなあ。

慣れない曲師と組んで懸命に演じるき太。でも笑いをとっていたよ
楽日に太福さんが選んだのは古典浪曲「紺屋高尾」。
末広亭だから落語でも演じられている演目を、と言ってやりはじめたけれど。
初日にかけた「陸奥間違い」は末広亭でもトリをとっておられた二代目広沢菊春先生台本の演目。師匠の玉川福太郎も演じていたもの。
楽日の「紺屋高尾」は、彼が大変にお世話になった、故・国本武春師匠の十八番。
先人へのリスペクト。
そして新作を売り物にしてきた彼が、10日間、古典と新作をきっちり半分ずつ演じました。
いやもうね、太福さん。楽屋への気遣い、出演者への気遣いからなにから。かなわないよ。お見事。
千秋楽の三本締め。

これは、ひとつの事件でした。
いったい、どういうことでこの祝祭感が生まれたのか。
本人曰く、なによりお客さんが喜んでくれているのが嬉しかった、みんな、おめでとうと言ってくれた、と。
おめでたい場にいられるって幸せですものね。その祝祭に、皆さん参加してくださったんですね。そんな場を、彼は生み出したっていうことです。

打ちあげは当然ながら盛り上がりました
玉川太福主任公演は、またあることと思います。
そして、そのうちに、もっと祝祭感のある場も、生まれるんじゃないかと思います。
そんな場にいられて幸せだった。
太福さん、ありがとう。
◆たまがわ・ななふく 横浜市出身。筑摩書房の編集者だった1995年、曲師(三味線弾き)として二代目玉川福太郎に入門。師の勧めで浪曲も始め、2001年に浪曲師として初舞台。古典から自作の新作まで幅広く公演するほか、さまざまな浪曲イベントをプロデュースし、他ジャンルの芸能・音楽との交流も積極的に取り組む。2018年度文化庁文化交流使としてイタリアやオーストリア、ポーランド、キルギスなど7カ国を巡ったほか、中国、韓国、アメリカでも浪曲を披露している。第11回伊丹十三賞を受賞。
◆「ななふく浪曲旅日記」は毎月第三土曜に配信します。

「玉川奈々福の有楽町でうなりましょう!~三山ひろし浪曲披露~」チケット発売中
https://ciy.digital.asahi.com/ciy/11015450
ななふく浪曲旅日記の新着記事
-
浪曲づくりは旅の記憶をたよりに しばらく旅公演がない奈々福さん。新作浪曲をつくりながら、かつての旅をネタとして盛り込みます。
-
お家芸の生まれ故郷、東庄町へ 浪曲師の玉川奈々福さんが受け継ぐ玉川一門の家の芸に「天保水滸伝」があります。物語の舞台となっている千葉県東庄町は奈々福さんにとって第二の故郷です。
-
大衆演劇との奇縁で実現した「節劇(ふしげき)」 かつて大衆演劇の追っかけをしていた玉川奈々福さん。数十年ぶりの再会が「節劇」という浪曲と大衆演劇とのコラボレーションを実現させました。
-
子どもたちのきらきらした目に感動 11月は旅から旅だった浪曲師の玉川奈々福さん。静岡で小学生に浪曲の実演とワークショップを開いたのですが……。